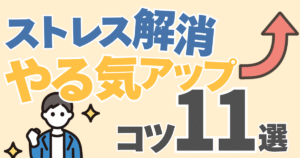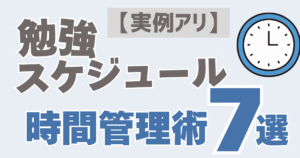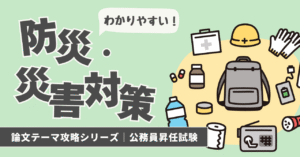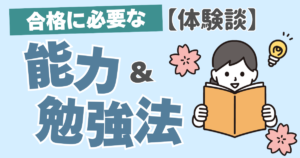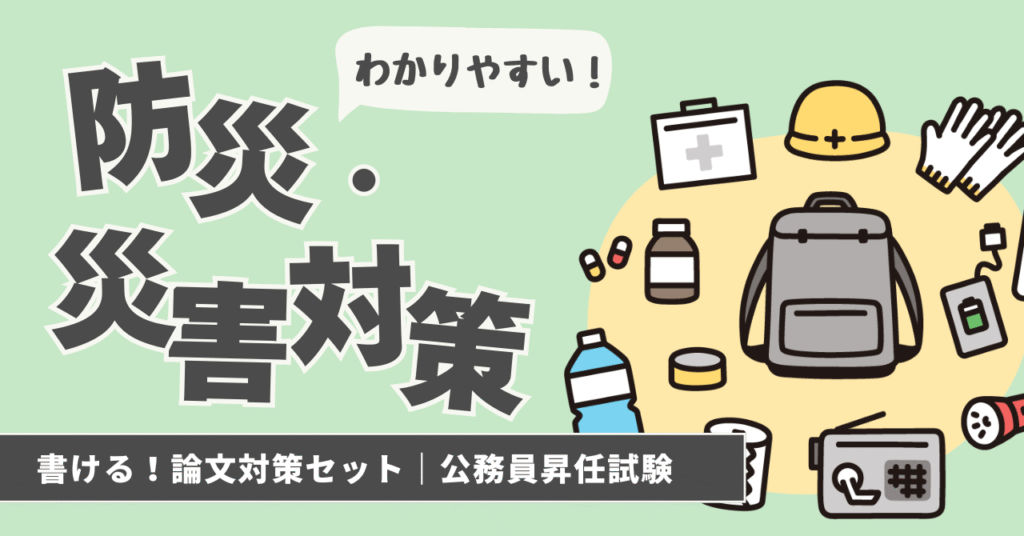「公務員の昇任試験って、どんな内容?」
「昇任試験を受けるタイミングは?」
公務員として働く上で、必ず通るのが「昇任試験」。
公務員になるには、試験に合格する必要があります。
しかし入庁してからも「昇任試験」という形で試験が続いていくのが公務員です。主任・係長・管理職など、様々なタイミングで昇任試験があります。
 ハル
ハル私もこれまでに3回、昇任試験を受けました!
私は運良くすべての昇任試験で1発合格することができ、33歳で組織内の最年少係長になった経験もあります。
この記事では、私自身の経験をもとに、公務員昇任試験の内容やタイミングについて詳しく紹介します。
公務員の昇任試験とは


昇任試験は、上位のポストに就くために必要な能力があるかを測る試験です。
その目的は主に以下の3つ。
- 昇任後の職位にふさわしい能力があるか測る
- 資格要件を満たす人に公平な受験資格を与えて公正な選考を行う
- 意欲のある人が昇任することで組織と個人のミスマッチを防ぐ
昇任試験は多くの自治体で実施されています。



主任、係長、課長補佐の昇任試験が行われることが多いですね
公務員昇任試験の種類とタイミング
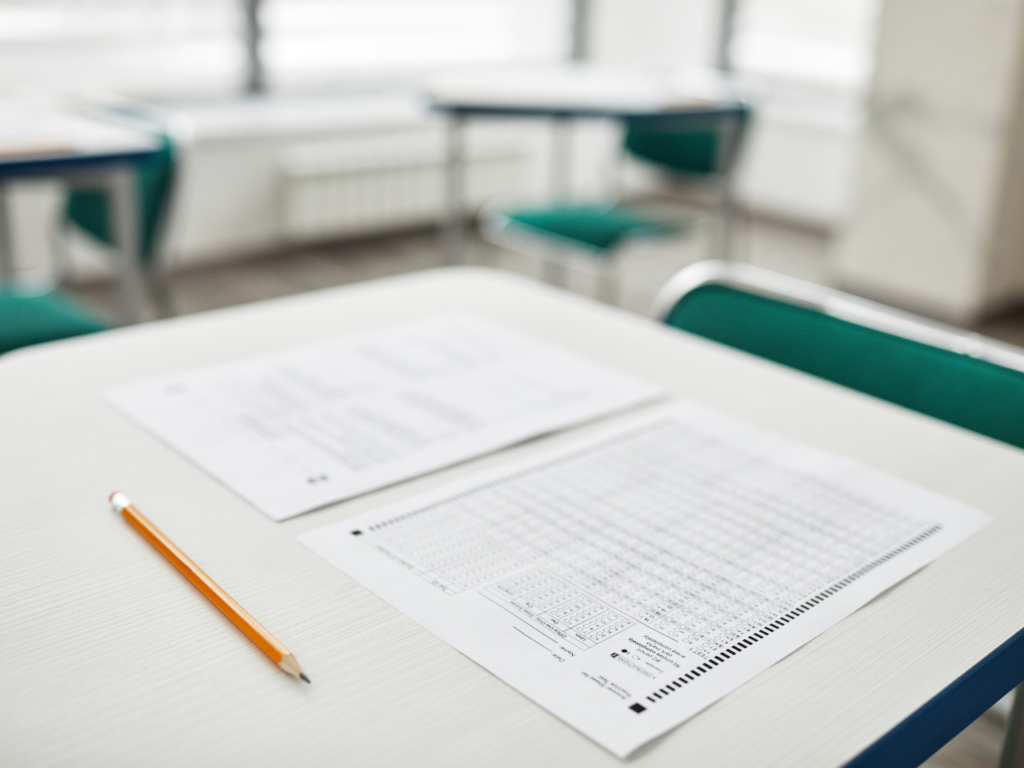
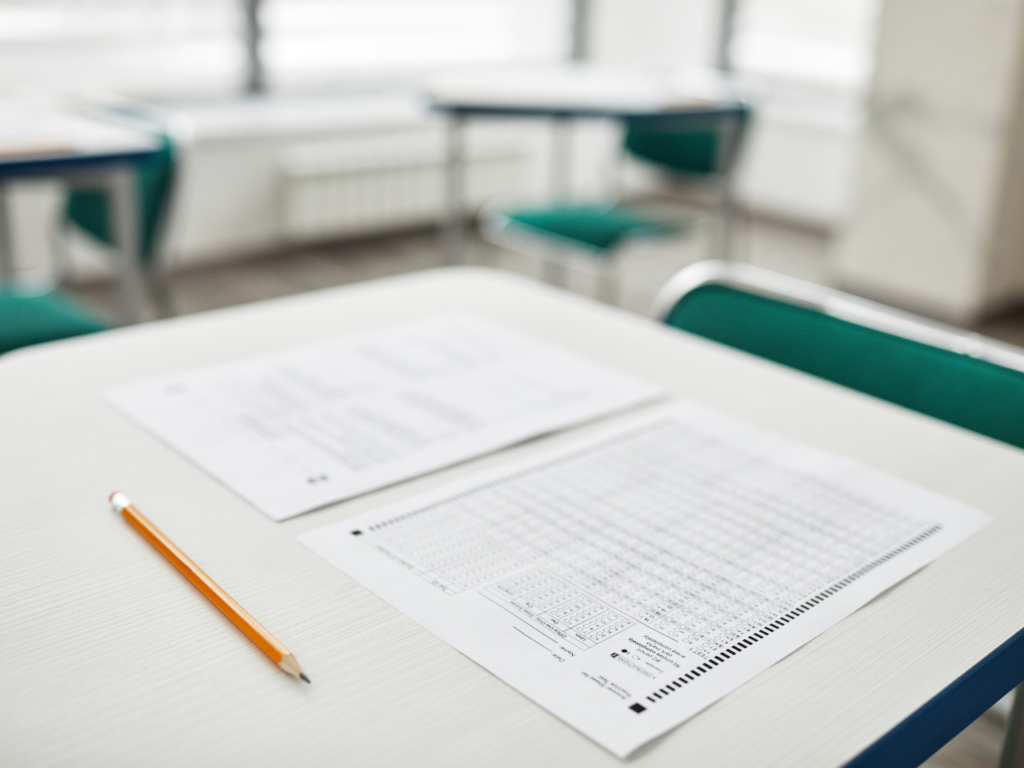
昇任試験の種類とタイミングは自治体によって異なります。
人材不足の背景から、昇任試験のタイミングが早まっている傾向にあります。
特に社会人経験枠で採用された場合、より早いタイミングで昇任試験を受けることも多いです。
今回は、大学卒業後に入庁した場合、主任・係長・管理職それぞれの昇任試験のタイミングや年齢目安について解説していきます!
主任試験
主任試験は、主任になるための昇任試験です。主任昇任試験がない自治体も多いです。
- 特徴:主任昇任試験がなく、経験年数や人事評価のみで昇任する自治体も多い
- タイミング:入庁から約6〜10年目
- 年齢目安:28歳〜32歳前後
係長試験
係長試験は、係長になるための昇任試験です。多くの自治体で係長昇任試験が行われています。
- 特徴:主任試験とは異なり、筆記や論文など総合的な試験が行われる
- タイミング:主任経験後、3〜5年程度
- 年齢目安:35歳前後
係長は、係のリーダーとして部下のマネジメントやチーム運営が必要になります。ここが主任との大きな違いです。
主任と係長の違い
主任の役割:実務を中心に担当しつつ、後輩職員の指導や業務調整を行う。係長への準備段階として位置付けられることが多く、主に個別業務や小規模なチームのサポートを担当。
係長の役割:チームや係全体の業務を統括し、責任者として意思決定や調整を行う。プレイヤー兼リーダー的な役割で、チーム全体の成果に責任を持つ。一般的には管理職ではないが、準管理職的な立場としてチームのマネジメントも必要。



係がない少人数の職場では「係長級の主任」がいることも
管理職試験
管理職試験は、課長補佐や課長といった管理職になるための試験です。
- 特徴:管理職試験がなく、人事評価や上司からの推薦により昇任する場合もある
- タイミング:係長経験後、5〜10年程度
- 年齢目安:課長補佐は45歳前後、課長は50歳前後
公務員昇任試験の内容


昇任試験の内容は自治体によって様々ですが、一般的には以下のような試験が行われます。
| 試験の種類 | 主任試験 | 係長試験 | 管理職試験 | |
|---|---|---|---|---|
| 受験のタイミング | 入庁から約6〜10年目 | 主任経験後、3〜5年程度 | 係長経験後、5〜10年程度 | |
| 年齢の目安 | 28歳〜32歳前後 | 35歳前後 | 課長補佐:45歳前後 課長:50歳前後 | |
| 求められる主な能力 | 基礎的な業務知識 問題解決力 指導力 | リーダーシップ 調整力 企画力 | マネジメント能力 政策形成能力 リスク管理能力 | |
| 試験内容 | 筆記試験 | ◎ | ◎ | ◯ |
| 論文 | ◯ | ◎ | ◎ | |
| 面接 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| プレゼン | △ | △ | △ | |
※ ◎:ほぼ必ず実施、◯:多くの場合実施、△:一部の自治体で実施
筆記試験
筆記試験は、多くの自治体で実施されています。
出題内容としては地方自治法・地方公務員法・行政法など。
試験形式は択一式が多いですが、一部の自治体では記述式のところもあります。
筆記試験では、基礎的な行政知識や法令の理解力が問われます。



主任や係長の昇任試験では、多くの自治体で筆記試験があります
論文
論文試験には「集合型(試験形式)」と「提出型」の2種類あります。
多くの自治体では「集合型(試験形式)」が採用されています。
難易度が高いのは「集合型(試験形式)」。
当日発表されたテーマに対して、短時間で良質な論文を書く必要があるからです。
「集合型試験」では、受験者が指定された日時に試験会場に集まり、その場で論文を作成する。
限られた時間で、良質な論文を書けるかがポイント。
- 制限時間内(通常60〜90分程度)に論文を書く必要がある
- テーマは当日発表される
- 即応力や短時間での文章構成力が求められる
論文試験のテーマとしては、行政課題や職場課題が出題される傾向にあります。
試験時間は通常60分〜90分。文字数は1,000〜2,000文字程度。
論文試験では、論理的思考や問題解決能力、文章表現力などが問われます。



論文試験は苦手な人が多く、ここが合否を決めるカギです
面接
昇任試験では、個別面接が行われます。面接時間は15分〜20分程度です。
面接官は通常2〜3人。人事担当者だけでなく、外部の人が面接を担当することもあります。
レポートなどの事前提出物がある場合、面接では関連する質問があるので準備しておくのがポイント。
ときには予想外の質問や事例問題が出題されることもあります。
面接試験では、人間性やコミュニケーション能力、リーダーシップなどが評価されます。



昇任試験の種類を問わず面接を行う自治体が多いですね
プレゼンテーション
一部の自治体では、昇任試験でプレゼンが行われます。
社会人経験枠で採用された場合、面接試験の代わりとしてプレゼンを実施している自治体もあります。
プレゼンは事前に決められたテーマをもとに、自分の意見や計画を発表します。
昇任試験のプレゼンでは、表現力や説得力、企画力などが評価ポイントです。
昇任試験では人事評価も重要
内閣府男女共同参画局の調査によると、人事評価を昇任や昇格の要素としている自治体も多いです。
特に課長補佐や課長などの管理職試験では、人事評価を重視する傾向にあります。
▼参考:内閣府男女共同参画局「昇任昇格等登用の考慮要素となる事項(都道府県・政令指定都市)」
昇任試験対策のポイント3選


事前準備をしっかりする
昇任試験に合格できるかは、どれだけ準備したかで決まると言えます。
筆記試験は対策しやすいので、しっかり準備しておきましょう。
自分に合った問題集を選んで、何周もくり返し解くことがポイントです。
論文は過去のテーマを分析し、基礎知識を身につけておくことが大切です。
どんなテーマが出題されるかは自治体ごとに特徴があるため、上司や先輩に聞いて情報収集するのがおすすめ。
実際にテーマに沿って論文を書いて、添削してもらうのも効果的です。
「今自分にできることは全部やり切った!」と思えるくらい、しっかりと事前準備を進めていきましょう。



合格者の中には「昇任試験は準備が9割!」と言う人もいました
スケジュールを立てて時間管理する
日々の仕事をこなしながら、昇任試験の勉強をするのは大変です。
部署や時期によっても忙しさは違うため、そんな中で昇任試験の勉強時間を確保するのはかなり難しいのが事実。
また仕事だけでなく、家事や育児などプライベートでもやるべきことはたくさんあります。
でも、やるしかありません。
どんな状況であっても、昇任試験に合格するためには勉強時間を確保する必要があります。
1日は誰もが同じ24時間。限られた時間をどう使うかは自分次第。
今の自分の環境の中で、どうやって時間をつくり出すかを考えるのが大切です。
- 1日のスケジュールを書き出し、やめること&やらないことを決める
- やるべきことの優先順位をつけてスケジュールに落とし込む
- やると決めたことは言い訳せずにちゃんとやり切る
時間管理スキルは、昇任してからも必要となる超重要スキルです。
自分の仕事はもちろん、後輩や部下のマネジメントやチーム運営も行う必要があるため、時間の使い方がより重要になってきます。



昇任試験は時間管理スキルを身につける練習にもなります
日々の仕事ときちんと向き合う
昇任試験は、試験本番だけが重要なのではありません。
昇任する前から今の自分にもできることがあります。それを見つけることが大切です。
- 目の前の仕事ときちんと向き合う
- 課題を見つけ、解決するために自分にできることを考えて行動する
- 「係長になったら○○をする!」ではなく「自分が係長の立場だったらどうするか?」を考え、今できることを実際にやってみる
試験官はこれまでに多くの受験者を見てきたプロ。どんな姿勢で仕事をしているのか、試験官にはわかります。
だからこそ、これを意識していれば論文や面接で大きな差がつきます。
「昇任したらやる」のではなく、「今の自分にできることからやってみる」
これが一番の昇任試験対策になると確信しています。



「今の自分にできることから小さく始めてみる」のが大事!
早めの準備が昇任試験合格への近道!


公務員昇任試験は、キャリアアップのための重要なステップです。
試験の内容やタイミングを見極め、早めに準備を始めることが合格への近道となります。
特に大切なのは、日々の業務に真剣に向き合い、今の自分にできることから挑戦する姿勢。
昇任試験はキャリアアップのためだけではなく、自己成長にもつながります。
この記事が、これから昇任試験に挑戦する皆さんのお役に立てばうれしいです。
計画的に準備を進めて、昇任試験の合格をつかみとりましょう!