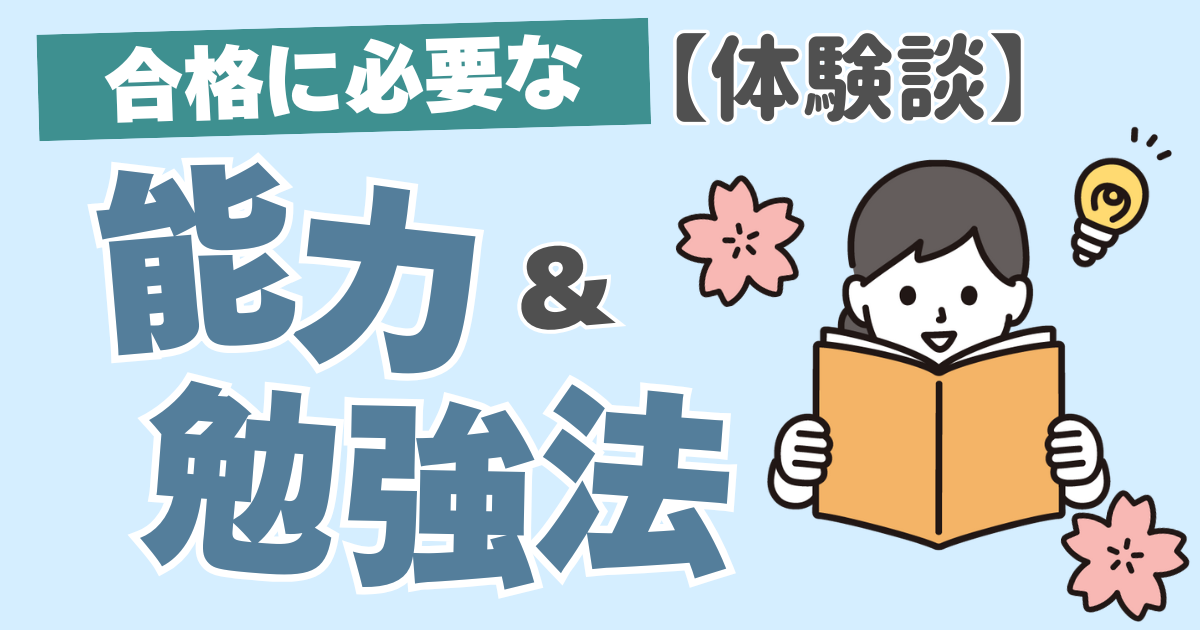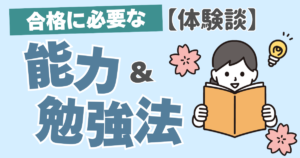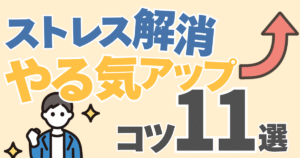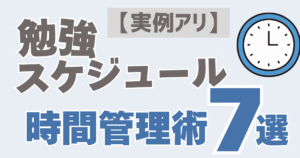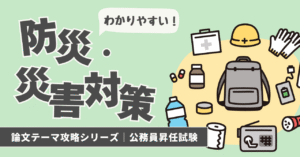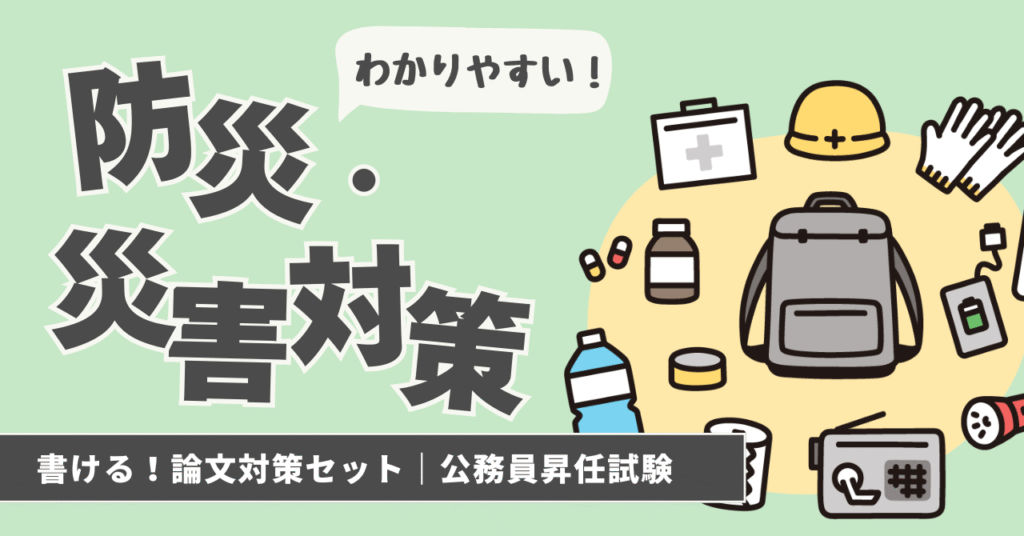昇任試験に合格するための勉強法を知りたい!
公務員昇任試験の合格に必要な能力は?
公務員として働いていると、いずれ直面するのが昇任試験。
自治体によって異なりますが、昇任試験の合格率は20%〜50%程度と決して高くありません。
 ハル
ハル日々の仕事をしながらどうやって昇任試験対策をすればいいのか、悩みますよね…
私はこれまでに昇任試験を3回受験し、運良くすべて一発合格できました。論文試験ではA評価を獲得したこともあります。
- 昇任試験の合格に必要な能力
- 昇任試験に合格するための勉強法と体験談
- 昇任試験に合格したらどうなるか
この記事では、昇任試験に合格するために必要な能力と具体的な勉強法について、私の体験を交えながら紹介します。
公務員昇任試験の概要


昇任試験として、主任・係長・管理職試験を行う自治体が多いです。
試験内容は自治体によって違いますが、一般的には筆記試験・論文・面接・プレゼンテーションなど。また人事評価も昇任試験では重要なポイントです。
詳しくは「【わかりやすい】公務員昇任試験の内容とタイミングを解説!」の記事にまとめています。
昇任試験の難易度、合格率は自治体によって大きく異なります。



いくつか具体例を紹介します
・新宿区の場合(令和5年度)
| 種別 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 主任 | 312人 | 65人 | 20.8% |
| 係長 | 97人 | 48人 | 49.5% |
| 課長補佐 | 42人 | 14人 | 33.3% |
・品川区の場合(令和5年度)
| 種別 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 主任 | 232人 | 110人 | 47.4% |
| 係長(人事評価のみ) | 303人 | 66人 | 21.8% |
| 課長補佐(人事評価のみ) | 92人 | 21人 | 22.8% |
| 管理職(種別Ⅰ類) | 25人 | 10人 | 40% |
このように、昇任試験の合格率は20〜50%程度と幅があります。



簡単ではありませんが、戦略を立てて準備すれば十分合格できる範囲です
公務員昇任試験の合格に必要な能力6選


昇任試験では単なる知識だけでなく、さまざまな能力が求められます。
今回は特に重要な6つの能力について紹介します。
- 知識・専門性
- 論理的思考力
- 問題解決能力
- 表現力・コミュニケーション能力
- リーダーシップ
- マネジメント能力
一つずつ解説していきます!
知識・専門性
昇任試験では、基礎的な法令知識として地方自治法・地方公務員法・行政法などが出題されます。
これは「公務員として仕事をする上で必要となる基本的なルールを理解しているか」を問うためです。
また技術職(土木、建築など)や専門職(保健師、栄養士など)の場合、それぞれの分野における専門知識も必要です。
知識・専門性は、筆記試験はもちろん、面接でも「なぜそのような判断をするのか?」という根拠として問われることがあります。
- 法律の暗記だけでなく「なぜそのような仕組みなのか」という背景も理解する
- 業務に関連する専門知識を人に説明できるよう整理しておく
- 新しい制度や法改正について常にアンテナを張る



面接試験では、普段どんな業務をしているかよく聞かれます。
自分の業務についてわかりやすく説明できるようにしておくと良いですね。
論理的思考力
論理的思考力とは、物事を筋道立てて考える力のことです。
- 事実と意見を区別する
- 原因と結果の関係を明確にする
- 前提から結論を導き出す
- 複数の事象の関連性を見抜く
論理的思考力はパズルを完成させることに似ています。バラバラの情報や事実から推測し、ピースを正しく組み立て、ひとつの絵をつくりあげていく力です。
論文では「主張に一貫性があるか?」、面接では「質問に対して的確に答えているか?」が評価されます。
- 日常的に「なぜ?」を考える習慣をつける
- 問題分析は5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識する
- 自分の考えを論理的に説明できるように練習する



文章は論理的思考力がわかりやすいので、論文の重要な評価ポイントになります
問題解決能力
問題解決能力とは課題を発見し、解決策を考え、実行する能力です。
- 課題を正確に把握する
- 複数の解決策を提示する
- 最適な解決策を選択し、実行計画を立てる
- 結果を評価し、必要に応じて修正する
論理的思考力が「考え方のプロセス」だとすれば、問題解決能力は「実際の行動につなげる力」だといえます。
スポーツに例えるなら、論理的思考力は「試合の戦略を立てる力」、問題解決能力は「実際の試合で状況に応じて最適なプレーを選ぶ力」です。
問題解決能力は「課題に対して適切な解決策を提案できるか?」といった視点で、論文や面接を通して評価されます。
- 日頃から職場の課題に意識を向ける
- 課題に対して複数の解決策を考える習慣をつける
- 解決策はメリット・デメリットを比較して考える
論理的思考力と問題解決能力の違い
論理的思考力は「なぜこの問題が起きているのか?」を考えるのに対し、問題解決能力は「この問題をどうやって解決するか?」を考える。
(例)論文試験:論理的思考力を用いて課題を分析し、問題解決能力を活かして実現可能な解決策を具体的に提案する
論理的思考力がない 主張に根拠がなく問題解決につながらない
問題解決能力がない 実現可能性がなく「絵に描いた餅」で終わってしまう



昇任試験では論理的思考力と問題解決能力の2つとも重要です
表現力・コミュニケーション力
表現力・コミュニケーション力とは「自分の考えを相手にわかりやすく伝える力」です。
いくら良いアイデアを持っていても、それを相手に伝えられなければ意味がありません。
- 簡潔で読みやすく説得力のある文章
- 相手の立場や理解度に合わせて説明する
- 複雑な情報をわかりやすく整理して伝える
昇任試験では「わかりやすく読みやすい文章を書けるか?」「明確で説得力のある説明ができるか?」が評価されます。
- 相手の立場に立って考える習慣をつける
- 難しい専門用語を使わず、簡単な言葉で説明する
- 説明するときや文章を書くときは結論から伝える



表現力・コミュニケーション力は、練習して磨きやすいのが特徴です
リーダーシップ
リーダーシップとは、チームのメンバーに影響を与え、目標達成に向けて導く能力です。
これは「命令する力」ではなく、「目標や方向性を明確に示し、メンバーの力を引き出す力」のことです。
- ビジョンや目標を明確に示す
- チームメンバーの強みを活かし、育成と動機づけを行う
- 適切な判断と決断を下す
- 困難な状況でも前向きな姿勢を保つ
- 責任を取る覚悟
リーダーシップは生まれつきの才能ではなく、学びと経験によって身につけていくことができます。
「立場が人をつくる」という言葉があるように、今自分にできることを一生懸命やることで、その立場にふさわしい人(人格)に近づいていきます。
リーダーシップを身につけるには、後輩や部下の育成に積極的に関わる意識を持ち、経験を積むことが大切です。



特に係長昇任試験ではリーダーシップが求められます
論文や面接での「あなたは係長として、どのようにチームの運営や部下育成に取り組みますか?」といった質問を通して、リーダーシップが問われます。
- 普段から部下や後輩の育成に積極的に関わり、経験を積む
- 「指示する」だけでなく「話を聴く」ことを意識する
- 自分の強みと弱みを理解し、自分に合うリーダーシップをとる
マネジメント能力
マネジメント能力とは、組織や事業を効率的・効果的に運営する力です。特に管理職試験ではマネジメント能力が重視されます。
マネジメント能力は、家計を管理するようなもの。限られた予算の中で、必要なものに優先順位をつけ、満足度を最大化する能力です。
- 人材管理(適材適所の配置、育成、評価)
- 予算管理(効率的な資源配分、コスト管理)
- 時間管理(優先順位づけ、スケジュール管理)
- プロジェクト管理(計画立案、進捗管理、成果評価)
- リスク管理(問題の予測と対策)
昇任試験では、論文や面接を通して「管理職としてチームやプロジェクトをどのようにマネジメントしていくか?」という視点で評価されます。
また人事評価を通して、日常業務での実績や目標達成状況が評価されることもあります。
- 予算管理や人材管理、プロジェクト管理の基本を学ぶ
- 自分の仕事の進め方を見直し、効率化や業務改善に取り組む
- 限られた資源(予算・人員・時間)の中で最大の効果を上げる方法を考える
リーダーシップとマネジメント能力の違い
リーダーシップ:組織の目標達成のためにメンバーを導き、影響を与える能力。「人を導き、変革を促す」ことに焦点を当てる。係長昇任試験で求められる。
マネジメント能力:成果を上げるための手法を考え、組織を管理・運営する能力。「リソースを管理し、効率を高める」ことに焦点を当てる。管理職昇任試験で必要となる。



管理職を目指すならマネジメント能力は不可欠です
【体験談あり】公務員昇任試験に合格するための勉強法
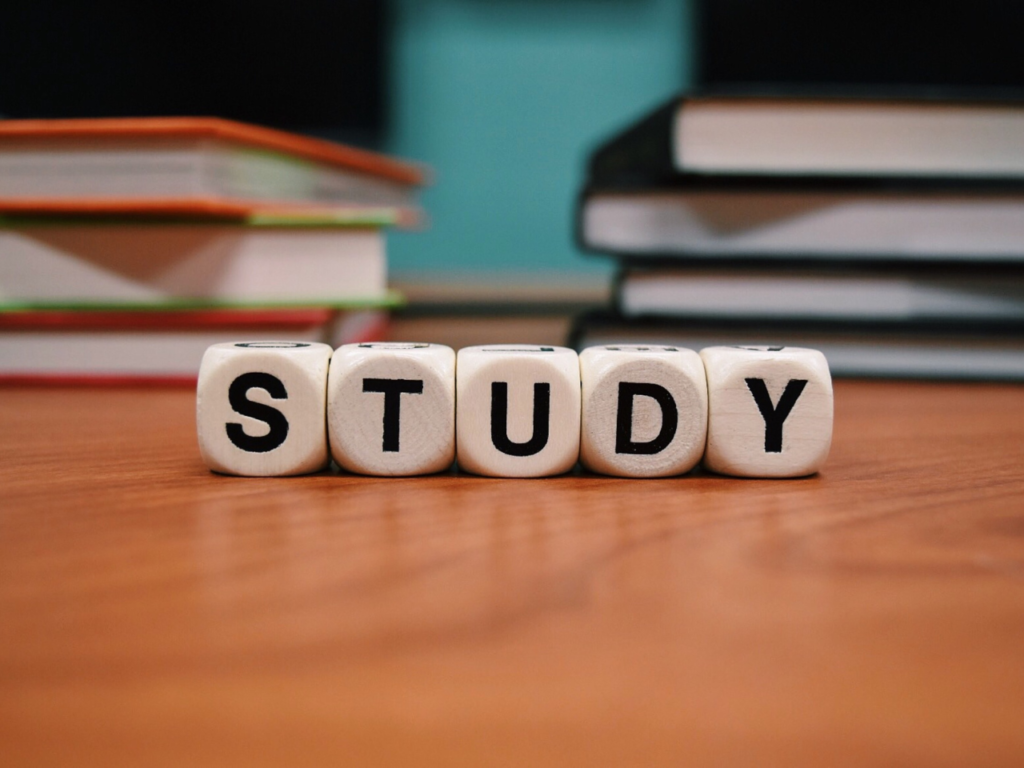
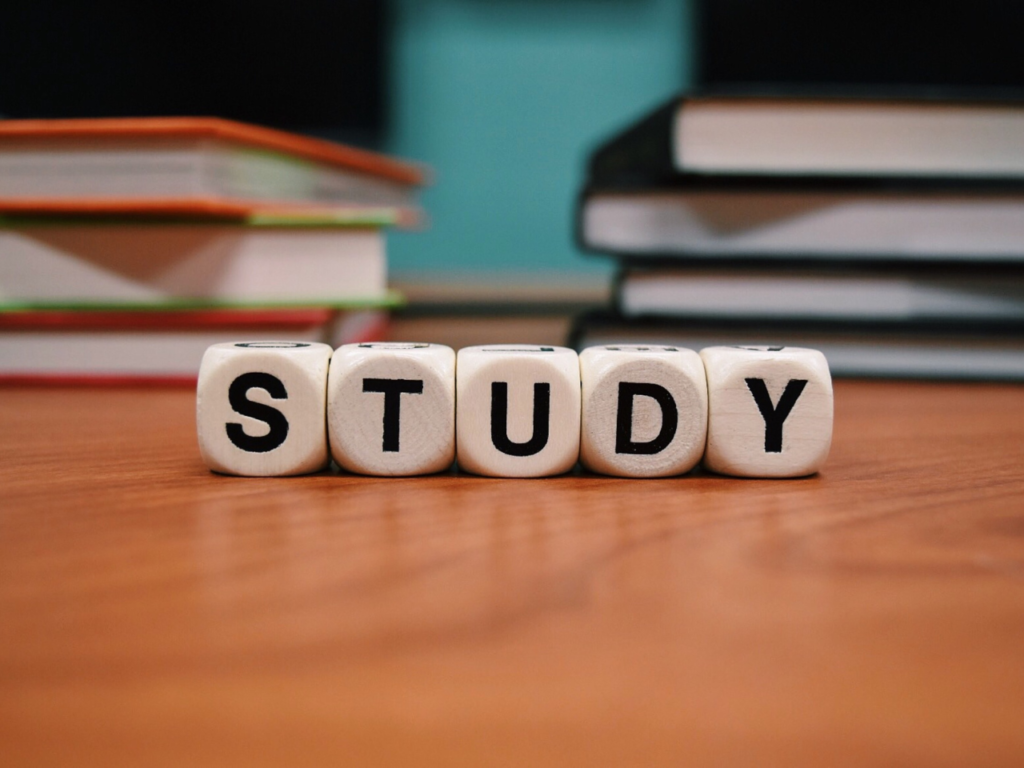
日々の業務をこなしながら昇任試験の勉強をするのは大変です。
重要なのは、まず試験の傾向と特徴を知ること。
そしてスケジュールを立てて早めに動き出し、戦略的に勉強を進めるのがポイントです。



試験内容は自治体ごとに違うため、まずは傾向と特徴をつかむのが大事!
筆記試験対策
筆記試験対策は、問題集をくり返し解くのがおすすめです。
問題集のメリットは、出題頻度の高い問題に絞って勉強できること。限られた時間で効率的に勉強を進められます。
- 口コミ評価が一定以上あるもの
- 解説がわかりやすく、自分に合っていると感じるもの
自治体によっては総務省の「e-ラーニング学習」を導入しているところもあり、動画で地方自治法や地方公務員法を学ぶことができます。



「e-ラーニング」は食事や家事をしながら勉強できるのがメリットです
筆記試験対策の進め方
私の場合、昇任試験の通知があったのは試験本番の約一ヶ月前。出題範囲は、地方自治法・地方公務員法・行政法の3分野です。
そのため短い期間で効率的に筆記試験対策をする必要がありました。
地方自治法・地方公務員法については、問題集は使用せず、「eラーニング」を活用しました。
- 試験当日までに「eラーニング」を3周した
- 動画の再生速度を「倍速モード」にして「聴く」ことを意識づけた
- 食事や歯磨き、家事をするときは必ず動画学習をセットにして習慣化した



座っていると眠くなるので立ったまま動画を見ていたことも
行政法は「eラーニング」の範囲外だったため、問題集を使って学習を進めることにしました。
使った問題集は、東京リーガルマインド「過去問解きまくり!12行政法」の1冊のみ。
- 問題集は「地方公務員上級」の出題頻度の高い分野に絞り、試験当日までに2周した
- 1問に対して考える時間をかけすぎず、10秒考えてわからない問題は解説を読む
- 理解度によって「✓」「△」「×」の3種類の印をつけ、優先順位をつけて復習する



行政法の問題集は3周するのが目標でしたが時間切れで2周となりました
問題集の使い方
問題集で重要なのは何度もくり返すこと。1回で完璧にする必要はありません。
人間は忘れる生き物だからこそ、何度もくり返すことが大切。時間をかけて取り組むより回転数を上げるほうが効果的です。
具体的には以下の流れで進めました。
問題を解く。10秒考えてわからない問題は解説を読む。
考える時間をかけすぎないようにするのが回転数を上げるコツ。
- 「✓」:正解した問題で内容まで理解できている
- 「△」:何となく正解したけど内容の理解は不十分
- 「×」:不正解
問題を解いた翌日に「△」と「×」の問題を復習する。
「×」が続く問題は、ChatGPTやPerplexity(パープレキシティ)などのAIを活用するのがおすすめ。
AIに「〜の問題についてわかりやすく解説して」と指示を出すと、補足説明してくれる。
問題に対する理解が深まるまでAIへの質問をくり返す。AIなら何度でも質問できるので便利。
問題集の最初に戻り、もう一度問題を解く。できれば試験当日までに問題集を3周する。
すべての問題に「✓」の印が3回つくまで問題集をくり返し解く。



問題集は「覚える」よりも「理解する」という感覚です
- 問題集は1回で完璧にすることを目指さない。回転数を意識する
- 10秒考えてわからない問題は解説を読む。考える時間をかけすぎない
- 忘れてもOK。少しずつ知識をすり込む感覚で進めていく
論文対策
論文対策としては、以下の流れで進めるのが効果的です。
- 過去の昇任試験でどんな論文テーマが出題されたか情報収集する
上司や先輩に聞くのが効果的 - 出題テーマに合わせて基礎知識を身につける
- 時事問題やニュースにアンテナを張り、自分の意見を持つ
- 実際に論文を書いてみる
- 自分が書いた論文を添削してもらう
私の場合、上司が過去の出題テーマを教えてくれました。
論文テーマは職場課題に関するものだとわかったので、試験前日に過去の出題テーマに目を通し、自分ならどう書くかを考えました。
私が特別な対策をしなかった理由は、もともと文章を書くのは得意なほうで、ブログなども書いていたからです。
日常業務では「自分が係長の立場だったらどうするか?」という視点で職場の課題を考え、今自分にできることから小さくやってみることを意識するようにしていました。
過去の出題テーマを知り、自分が日々の業務で考えていること実践していることを言語化すれば、論文試験にも十分対応できると考えたのです。



論文試験の本質は「自分の考えをわかりやすく相手に伝えること」です
実際に試験当日は、過去のテーマとよく似たものが出題されました。
私自身、普段から書く習慣があったこと、文章を書くことに苦手意識がなかったことは大きいと思います。
もしそうでない場合、事前準備をしっかりしておくことが重要です。
論文は、昇任試験の中でも合否を分けるカギになる重要な試験です。苦手な人も多いからこそ、しっかり準備すればここで差をつけることができます。
面接対策
面接では過去・現在・未来についての質問を通して、あなたが何を考え、どう行動するかが問われます。
具体的に次のような質問について考え、自分の頭の中を整理し、言語化しておくのが効果的です。
過去について
- これまでの職務経験と具体的な実績は?
- 仕事を通じて学んだことは何か?
- 壁にぶつかったときどう乗り越えたか?
現在について
- 現在の職場で課題だと感じていることは?
- 仕事をする上で大事にしていることは何か?
- あなた自身の強みと弱みは?
未来について
- 昇任したらどのような係長(管理職)になりたいと思うか?
- 今後の目標や挑戦したいことは何か?
- 組織やチームに対してあなたはどのように貢献できるか?
また、実際に口に出して練習するのも効果的です。自分の考えや想いを言葉にしてわかりやすく伝えるのは、意外と難しいもの。
おすすめは鏡の前で話してみること、動画で撮影すること。きっと自分のクセに気づくはずです。
話の途中に「えー」「あのー」が多い
声が小さい
早口で何を言っているのか聞き取りにくい
身振り手振りがまったくない(多すぎる)
表情が固い
視線が定まらない
自信がないように見える
「自分はこんなふうに見えているんだ」これに気づくことがスタート。
自分のクセを知ることで、どうすればいいかを考え、改善につなげられるのです。



これをやったことのある人とない人では、面接で大きな差が出ます
私は、話すのが得意というタイプではありません。それでも今までの面接試験は何とかなりました。
もちろん緊張します。でも、緊張してもいい。話すのが得意じゃなくても大丈夫だと思っています。
私が面接試験で大事にしていたのは、熱量を込めて自分の言葉で伝えること。
うまく話そうとしなくても、熱量を込めて伝えようとすれば、その姿勢は相手に必ず伝わります。
相手の立場に立って、相手が知りたいことにちゃんと答えることも重要です。
コミュニケーションはキャッチボールと同じ。相手の投げたボールをしっかり受け止めて、相手が取りやすいようにボールを投げるのが大切です。
自分が話したいことだけ話すのは、相手を無視してボールを投げる行為です。



思いやりがないとコミュニケーションは成立しません
嘘をつかないことも大切。嘘をついて無理につじつまを合わせようとすると、話のどこかに矛盾が生じます。
わからないことは素直に「申し訳ありませんが、わかりません」と言って大丈夫です。
でも「わかりません」だけで終わらせず、そこからどうするかを考え、伝えること。
相手の質問をきちんと受け止め、前向きに考えていることを伝えましょう。
- 熱量を込めて自分の言葉で伝える
- 相手の質問をしっかり受け止め、相手の知りたいことに答える
- 嘘をついたり見栄をはったりしない
プレゼン対策
一部の自治体では、政策提案などのプレゼンテーション試験が行われることがあります。事前に決められたテーマに沿ってプレゼンを行うため、準備が重要です。
- 結論を最初に伝え、わかりやすい構成にする
- ストーリーを意識し、聞き手の感情がどのように動くかを想像する
- 専門用語や難しい言葉はできるだけ使わず、簡潔な表現を心がける
- データや自分の実体験を含めて、具体的で説得力のある提案をする
プレゼンは面接試験と同様に、鏡の前で練習すること、動画で撮影することが効果的です。
プレゼンは、練習すれば必ず上達します。
そして練習を積み重ねることで、「自分はこれだけ準備してきた」という試験本番での自信につながるのです。



プレゼンは準備が8割。しっかり準備して試験に臨みましょう!
昇任試験に合格したらどうなる?


実は「昇任試験に合格=昇任する」のではありません。昇任試験に合格すると、「昇任候補者名簿」に掲載されます。
昇任試験に合格すると…
昇任候補者になる
昇任する
昇任者はこの名簿の中から選ばれますが、いつ昇任するかのタイミングは人によって異なります。
早ければ翌年4月に昇任することもある一方、昇任試験に合格後、10年以上昇任しない人もいます。
私が感じた昇任することのメリット・デメリットは、以下のとおりです。
- 入ってくる情報のスピードが速くなり動きやすくなる
- 給与や手当が増える
(昇任していない場合でも、昇任候補者になるとボーナスに「役職加算」がプラスされる) - 国の省庁派遣に推薦されるなど新たなキャリアの可能性が広がる
- 業務量が増える
- 組織の目標達成に対する責任とプレッシャーが増す
- 難しい場面での意思決定や判断が求められる
簡単に言えば、それまではプレイヤーとして自分の仕事をするだけだったのが、その仕事に加えて部下やチームのマネジメントといった仕事もする必要があります。
業務量が増え、複雑なクレーム対応や困難な業務も担い、自分の責任で判断することが求められるようになります。



昇任後の4月は時間が溶けるように過ぎました…
「もしも徳川家康が総理大臣になったら」という映画の中で、豊臣秀吉が言ったセリフ。
トップとしてやるべきことは3つ。
映画「もしも徳川家康が総理大臣になったら」@豊臣秀吉
決めること
信じて任せること
責任を取ること
昇任することはトップになるのとは違いますが、この言葉には共感するところが多くありました。
昇任すると立場が変わり、今まで見えなかったものが見えるようになることがあります。
部下の育成やチーム運営など、難しさを感じる場面もたしかに多いです。
でも、結果として多くのことを学ぶことができ、貴重な経験を得られました。



昇任したことは自分の人生にとってプラスになっていると感じます
早めの準備と適切な戦略で昇任試験合格を目指そう!


昇任試験合格に重要なのは、早めの準備と適切な戦略。
必要な能力を理解して効果的な勉強法を実践すれば、昇任試験合格は決して届かない目標ではありません。
- 論理的思考力やリーダシップなど必要な能力を磨く
- 試験の特徴をつかみ、筆記試験や論文などそれぞれに効果的な対策を実践する
- 昇任するメリット・デメリットを理解した上で、自分のキャリアを考える
たしかに日々の仕事と試験勉強を両立させるのは大変です。
しかし昇任試験にチャレンジする過程で得られる知識や経験は、必ず自分にとってプラスになります。



昇任試験に挑戦する中で、時間をより大切にするようになりました
焦らずに自分のペースで、今できることからひとつずつ小さな行動を積み重ねて、試験合格に向けて進んでいきましょう!
「論文対策についてもっと詳しく知りたい」という方は、noteの論文対策に関する以下の記事もぜひご覧ください↓
昇任試験にチャレンジする皆さんを応援しています!